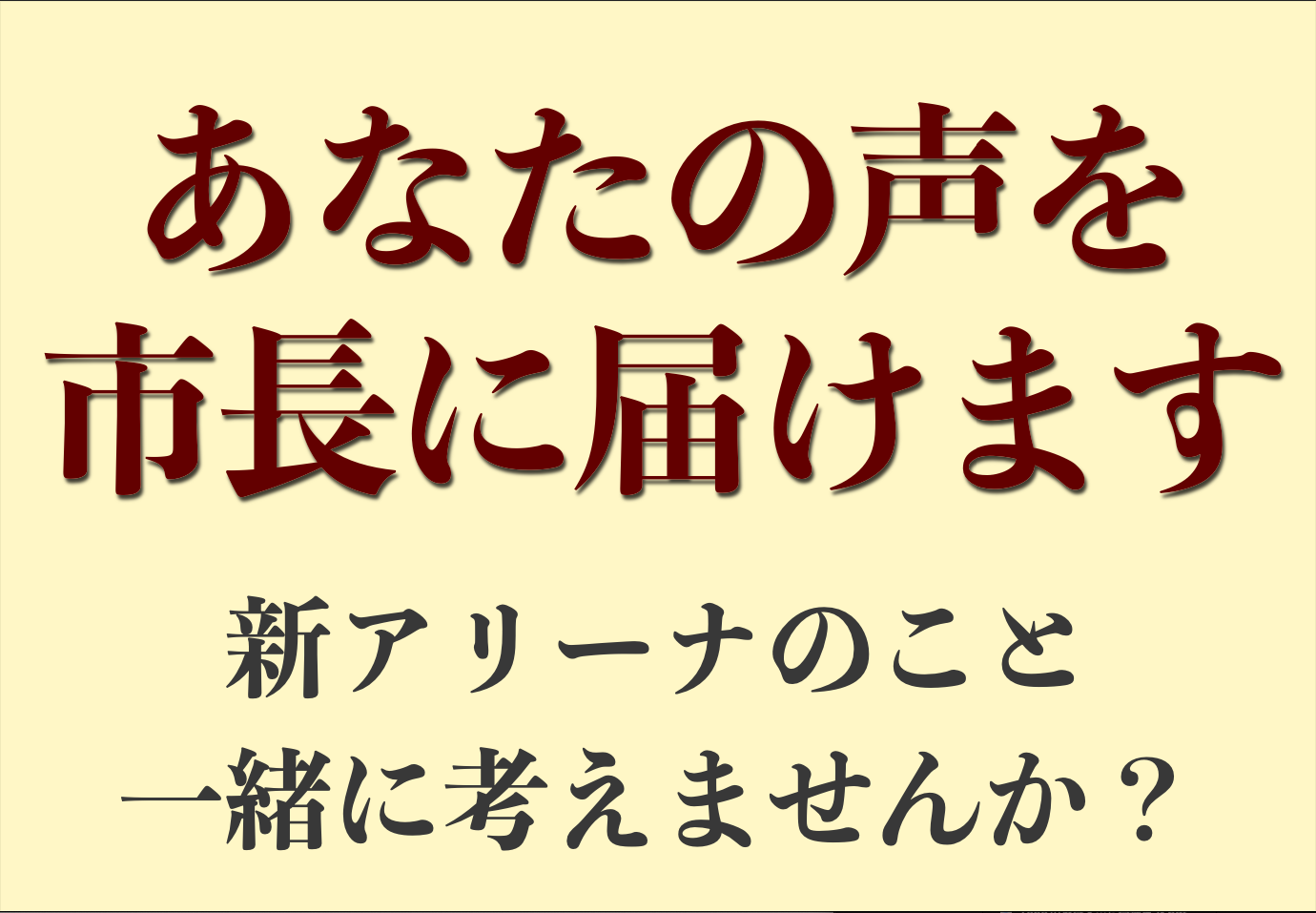私の暮らす豊橋市で、見過ごせない動きが続いています。
アリーナ建設をめぐる一連の経過は、私たちの民主主義のあり方そのものに問いを投げかけています。
2024年11月、新アリーナ計画の中止を公約に掲げた長坂尚登市長が、約4万5千票を得て当選しました。選挙は、私たち市民の意思をもっともはっきり示す場です。その結果として、市長は契約解除に向けた手続きを始めました。ところが、アリーナ推進派が多数を占める市議会は、契約解除に議会の議決を必要とするよう条例を改正しました。これは市長の権限を制限し、二元代表制のバランスを崩すものでした。
そして今、新たに「住民投票」が決まりました。本来、住民投票は民意を丁寧だとにすくい取るための制度であり、否定されるものではありません。しかし今回のケースでは、その運び方に大きな疑問があります。
2023年12月には、アリーナに「賛成」する立場からも「反対」する立場からも、住民投票条例案が提出されましたが、どちらも議会で否決されました。制度的な課題があるとの理由からでした。ところが、そうした問題が解決されないまま、推進派による条例案が再び提出され、今回は可決されたのです。
この変化は、「住民投票さえ実施できれば、アリーナ建設を正当化できる」という発想が背景にあるのではないかと疑いたくなります。手続きが公平でないまま制度が使われることで、意見の多様性や慎重な議論が置き去りにされてしまっているのではないでしょうか。
そして何より、アリーナ建設そのものに多くの懸念がある中で、議論を深める前に「数の力」で物事を進めようとする姿勢には強い違和感を覚えます。こうした構図こそが、多数派の暴力と言えるのではないかと私は感じています。
住民投票は、本来であれば、意見の違いを尊重しながら意思決定を行うための制度です。しかしそれが、一方向に市民の声を押し込めるための道具として使われてしまうなら、民主主義を守るどころか、かえって損なうことになります。
今、私たちは「民意」という言葉にただ従うのではなく、その裏側で何が起きているのかを見つめ直す必要があるのではないでしょうか。